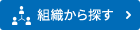新市まちづくり計画(米原市・近江町)について
更新日:2024年08月26日
新市まちづくり計画は、米原市・近江町の合併後の新市を建設していくための基本方針とこれに基づくまちづくり計画を策定し、その実現を図ることにより、1市1町の速やかな一体性の確立を促進するとともに、地域の個性を活かしながら、均衡ある発展と住民福祉の向上を図るものです。
なお、新市の進むべき方向についてのより詳細かつ具体的な内容については、新市において策定する基本構想、基本計画、実施計画に委ねるものとします。
新市まちづくり計画 米原市・近江町 (PDFファイル: 3.7MB)
合併の必要性
米原市・近江町は、古来からヤマトタケルの神話や息長族の繁栄、交通の要衝としての中世・近世の歴史など、文化・経済にわたって強い結びつきをもっており、住民の日常生活でも相互の交流が活発な地域です。
一方、加速度的に変化する時代の潮流の中で、地方分権の進展、少子高齢化の進行、多様化・高度化する行政ニーズ、国・県における構造改革などに対応するため、市町村においては、住民と行政とのパートナーシップのもと、効率的・効果的な行政運営が求められています。
自己決定・自己責任の原則に立つ地方分権時代においては、自分でできることは自分でする、地域でできることは地域で行う、それでできないことは行政が支援するという役割分担と連携が必要となります。
1市1町の合併は、このような行財政改革と特色ある地域づくりのための有効な手段と考えられます。
1 地方分権自立のために
1 地方分権への対応
地方分権時代がスタートした現在、市町村は、住民に最も身近な基礎的自治体として、自己決定・自己責任の原則を基本として、地域の個性を活かした自立的な行政の運営が求められています。
市町村は多くの権限を得るかわりに、高度な行政判断を要する事務事業が増えるため、専門的な知識や政策形成能力のある職員の育成と行政需要に的確に対応できる行財政基盤の確立が必要となります。
2 多様化・高度化する行政ニーズへの対応
住民生活の質的な変化に伴って住民ニーズが多様化・高度化しているだけでなく、今後の社会潮流をふまえれば、福祉、環境、教育など住民に身近な分野で、たえず新たな行政課題が生まれることが予想されます。
このため、専門職員の育成や一人ひとりの職員の能力向上により、自立的な行政運営を推進する必要があります。
3 地域自立と個性ある地域づくり
地方分権時代の中で、市町村は、地域の特色を活かしながら、都市としての魅力を高め、地域間競争の時代 を切り拓いていかなければなりません。
このため、住民と行政とのパートナーシップのもとに、地域の人材や資源を活かす総合的なまちづくりを推進することによって、より自立的で個性のある地域づくりを進める必要があります。
2 社会資本をより広く活かすために
住民の日常生活圏が拡大するとともに、地域の経済活動もますます広域化しています。
本地域に整備された高速道路や新幹線などの広域交通網や福祉・教育・文化等の公共施設などを活かして、住民の生活行動範囲に対応し、より活力ある地域基盤を形成するためには、広域的な視点に立ったまちづくりを展開する必要があります。
3 少子高齢化にしっかりと対応するために
全国的な少子高齢化の進行は本地域でも例外ではなく、高齢化傾向は全国や滋賀県の水準を上回っています。
このため、少子高齢化に伴って多様化・高度化する保健・医療・福祉・介護ニーズに的確に対応し、子どもの健やかな育成を支援する環境づくりや若者の定住促進、いつまでも元気に暮らせる地域づくりなど、より高度で一体的なサービスを提供できる体制の確立や専門的な人材の確保を図る必要があります。
4 より確かな行財政基盤確立のために
国・県における「構造改革」の取り組みは、大幅な財政赤字に対応しながら、経済を活性化させるためにも必要不可欠な課題となっており、国においては「三位一体の改革」として国庫補助金や地方交付税制度の改革が進められています。
今後は、これまでのような依存財源の確保が期待できない状況にある中で、行政サービスを低下させることなく経費を削減し財源を生み出す必要があります。行政改革のための有効な手段として合併を取り入れることにより、住民本位の行政サービスを提供していくためのより確かな行財政基盤を確立する必要があります。
- この記事に関するお問合せ先