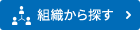国民健康保険税の算定方法
更新日:2025年04月01日
国民健康保険税の内訳について
国民健康保険税は、「医療給付費分」・「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分(40歳から64歳まで)」を合わせた額を納めていただきます。
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
|---|---|---|---|
| 40歳未満の人 | 納付 | 納付 | 納付の必要はありません |
| 40歳以上64歳以下の人(介護保険第2号被保険者) | 納付 | 納付 | 納付 |
| 65歳以上74歳以下の人(介護保険第1号被保険者) | 納付 | 納付 | 介護保険料として別に納付が必要です |
【注意】年度途中で65歳になられる方は、誕生月の前月までの介護納付金分を当初課税時(6月)から3月までの年10回(期)で納めていただきますので、介護保険第2号資格喪失にともなう国民健康保険税の額の変更はありません。
年度途中で40歳になられる方は、誕生月から翌3月までの介護納付金分を誕生月の翌月から納めていただきます。(4月が誕生月の方はその年の6月から)
国民健康保険税の算定方法について
国民健康保険税額は、所得割・均等割・平等割の3項目の合計額で、世帯ごとに算出し、世帯主が納税義務者となります。
| 項目 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
|---|---|---|---|
| (1)所得割 | 基準総所得金額(注1)×6.39パーセント | 基準総所得金額(注1)×2.8パーセント | 基準総所得金額(注1)×2.36パーセント |
| (2)均等割 | 被保険者1人当たり27,500円 | 被保険者1人当たり11,900円 | 被保険者1人当たり12,100円 |
| (3)平等割 | 1世帯当たり18,600円 | 1世帯当たり8,000円 | 1世帯当たり6,000円 |
| 賦課限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
- 1年間(年度)の国民健康保険税額は(1)(2)(3)の合計額です。
- 年度途中で、世帯被保険者に異動(加入や喪失、所得更正等)があった場合は、国民健康保険資格異動手続き後に再計算を行い、翌月に更正通知書を送付します。
- 擬制世帯(注2)の世帯主(擬制世帯主)の所得や人数は、(1)所得割額、(2)均等割額に含まれません。
- 賦課限度額とは、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれに設定されている1世帯ごとの国民健康保険税の上限額のことです。
(注1)前年中の所得金額から、地方税法第314条の2第2項に規定する額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を引いた金額
(注2)国保被保険者の属する世帯で世帯主が国保被保険者でない世帯
【注意】上記表中の(1)所得割額は被保険者ごとに算出し、世帯で合計します。被保険者の前年中の所得金額から地方税法第314条の2第2項に規定する額を差し引いた金額に税率を乗じた金額が課されます。
上記表中の(2)均等割は被保険者の人数に応じて課されます。(被保険者が未就学児の場合、均等割の5割が軽減されます。)
上記表中の(3)平等割は被保険者の人数に関係なく、1世帯ごとに課されます。
所得割の算定に用いる所得について
所得割の算定には、総合課税分の給与所得、公的年金等の雑所得、事業所得等の所得と、分離課税分の株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得(特別控除後)、山林所得等の所得を用います。
- 障害年金、遺族年金、雇用保険などの非課税所得は含まれません。
- 一時金として受け取る退職所得は含まれません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
国民健康保険税は75歳誕生月の前月分まで課税されます。
75歳の誕生日以降は国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されます。国民健康保険税は誕生月の前月分までで計算され、誕生月分からは後期高齢者医療保険料を納めていただきます。国民健康保険税の年税額はあらかじめ75歳到達による国民健康保険からの離脱を加味して計算します。
転入された方の国民健康保険税は後日変更されることがあります。
国民健康保険税の税額は前年中の所得をもとに計算しますが、令和7年1月2日以降に転入された方の所得は以前にお住まいの市町村に照会することになります。算定時点までに所得確認ができない場合は、軽減判定を行わずに、所得割以外(均等割、平等割)で税額を計算して課税させていただき、翌月以降に税額を更正しますのでご了承ください。
令和7年度版 国民健康保険税 試算
(注) 仮計算のため、参考額としてご利用ください。(条件により正しく計算できない場合があります。)
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
メールフォームによるお問合せ