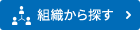施政方針(令和7年第1回米原市定例会)
更新日:2025年02月21日
はじめに
令和7年、2025年は米原市が誕生して20年を迎える節目の年となります。
これまでの20年間を振り返りますと、米原市にとって成長と変化のための大切な苗を植える時間でした。
合併当初は、さまざまな課題が山積し、行政サービスの統一、市民や地域での意識の違いなど、多くの課題や困難がありました。しかし、私たちは市民の皆さんや地域の声を大切にしながら、その一つ一つに真摯に向き合い、新しいまちを自分たちの手でつくっていこうという意気込みで歩んでまいりました。
そして、子ども、若者、子育て世代への支援、地域の支え合いの仕組みづくりなど、市民のくらしを支える取組を重点に、まちの基盤づくりに取り組んでまいりました。
また、合併以来の念願であった市役所新庁舎の建設、米原駅東口周辺まちづくり事業の進出事業者の決定など、本市の発展、未来への投資を進め、市民の皆さまをはじめ、議会の皆さまの御理解と御協力があったからこそ、20周年を迎えることができたと深く感謝を申し上げます。
さて、この20年間あまり、日本の人口は2007年(平成19年)をピークに、緩やかに減少し始め、今後、加速度を増して減少していきます。
米原市においても合併当初、約42,000人であった人口は、約37,000人まで減少し、子どもの出生数も令和5年、令和6年と2年連続で200人を下回る厳しい現実をつきつけられています。
2014年、東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全体の活力を上げることを目的として、国が地方に情報、人材、財政を支援するかたちで始まった「地方創生」。本市においても、人口減少に立ち向かう、まちの未来への羅針盤である「まち・ひと・しごと米原創生総合戦略」を策定し、子ども・若者・子育て世代、教育への支援や、「びわ湖の素 米原」をコンセプトとしたシティセールスによるまちの魅力を発信し、人口減少に立ち向かい、持続可能なまちづくりを推進してきました。
この間、新型コロナウイルス感染症の流行を経験し、私たちの働き方やライフスタイル、価値観の変化をもたらす中、自然豊かな環境や広々とした空間、地元の温かいコミュニティ、安全で静かな生活環境が評価され、地方への関心が高まりました。
しかしながら、経済活動、企業集積の中心である都市部には、地方にはない多様性、利便性、ビジネスチャンスがあるとされ、女性や若者が魅力を感じ、都市部に引き寄せられる要因にもなっており、むしろ東京一極集中は加速し、特に女性や若者の流出が止まらず、地方の高齢化、過疎化は進んでいます。
米原市誕生からの20年間の取組・成果を振り返り、引き続き、向き合うべき最大の課題は『人口減少』であると改めて認識すると同時に、この現実を悲観せず、人口減少に対応できるまちづくりに取り組まなければなりません。
50年、100年後を見据え、みんながずっと、幸せに米原で暮らすことができるようにするために、これまで耕してきた米原というフィールドを生かし、令和7年度はまちの未来へのタネを蒔き、芽を育む年にしてまいります。
令和7年度最重点施策
人口減少は、社会のさまざまな課題が顕在化する一方で、多くの可能性も生まれます。
労働力不足の課題に対しては、働き方改革の推進やデジタル技術の活用による効率化が期待されるなど、新たな可能性や課題に目を向けていく視点も持っています。
これまでの20年間、人口減少、少子化、地球温暖化、災害の頻発化と激甚化、経済活動の低迷、地域活力の低下、価値観の多様化などを経験したことで、私たちは従来の社会の仕組みを見直し、より豊かな社会を築く出発点に立っています。
令和7年度は、人口減少をマイナスとして捉えるのではなく、前向きに受け入れ、その課題を解決するためのアプローチとなる5つのタネを蒔き、市民の皆さんと一緒に、まちの未来に向けて大事に育ててまいります。
それでは、このタネとなる主な事業について申し上げます。
重点1.力強さのタネ(災害に強い安全な米原)
木造住宅の耐震化促進、地域防災計画の見直し
近年、自然災害が相次いで発生し各地で大きな被害をもたらしています。特に甚大な被害が予想されている南海トラフ巨大地震については、今後30年間の発生確率が80パーセントとされ、昨年、臨時情報が出されたところです。
災害に強く、誰もが安心して生活できる住環境を整備するため、木造住宅の耐震診断員派遣や各種補助制度の情報発信を行い、災害に備える意識の高揚を図るとともに、木造住宅耐震改修等事業補助金を拡充し、防災・減災対策を推進します。
また、昨年発生した伊吹地先土砂災害や能登半島地震の教訓を踏まえ、災害が起こることを前提とした適切な対応策を講じることが求められています。防災備蓄物資の更新や避難所の環境を充実させるとともに、より実効性の高い地域防災計画とするため、国の最新の指針等を反映したものに見直します。
市道伊吹太平寺線落石防護柵の設置・勝山谷川の浚渫
昨年、3回に渡って伊吹地先で発生した土砂災害では、人的な被害はありませんでしたが、被災のたびに、道路や水路、宅地内への土砂の堆積が繰り返され、市民の命と財産が脅かされる事態となりました。
こうした事態を二度と繰り返さないよう、市では、市道伊吹太平寺線への落石防護柵の設置や勝山谷川の定期的な浚渫を行うとともに、砂防・治山えん堤の新設などの滋賀県事業とも連携し、被災発生リスクの軽減や周辺地域の安全確保を図ってまいります。
伊吹山植生復元プロジェクト
市内外の企業様や伊吹山を愛する皆さまから応援いただいている伊吹山植生復元プロジェクトでは、ニホンジカの捕獲、南側斜面の崩壊防止対策と植生回復、そして山頂や3合目での植生保全の3つの取組をさらに強化するとともに、更なるPR活動を進め、伊吹山の再生に向けた応援の輪を広げてまいります。
重点2.安心のタネ(すべての人が安心して暮らせる米原)
移動市役所
地域では人口減少や少子高齢化等により、市役所への移動に課題のある高齢者が増えており、デジタルを活用した「行かない市役所」を目指し、行政サービスのデジタル化を進めています。しかしながら、移動に課題のある方には、デジタルの申請や手続をためらう方も多く、さらに、地域コミュニティの希薄化や自治会などの地域機能の存続に関する課題が多様化・複雑化しており、これまでの手法では行政サービスが届きにくくなっています。
人口減少に対応しつつ、地域で安心して住み続けられる持続可能な行政サービスへの転換を図るため、マイナンバーを活用したオンライン申請や遠隔相談システムなどを搭載した、さまざまな用途に活用できるマルチタスク車両を移動市役所として運行し、デジタルと、対面によるアナログの良さを生かした行政サービスと安心を地域に届けられる仕組みを県内で初めて運用します。
また、移動市役所と民間事業者が実施するサービスなどを並行して実施することで、地域コミュニティの活性化と持続可能な地域づくりを進めます。
地域医療構想、開業医誘致補助制度
人口減少、高齢化は地域医療に深刻な影響をもたらします。医師をはじめ、医療従事者の数が減少し、地域医療を支える人材不足、医療提供体制の脆弱化につながります。
公的な病院を持たない本市において、市民が安心して住み続けられる医療提供体制の安定と充実を目的として、地域医療構想の策定と開業医誘致補助制度の見直し・拡充を行います。
小中学校体育館空調設備の整備
近年、地球温暖化の影響から体育館における熱中症のリスクが高まっており、教育活動や災害時の避難所としての側面から、空調設備の整備が求められています。子どもたちの安全快適な教育環境および避難所としての環境を向上させるため、小中学校体育館の空調設備を整備します。
重点3.暮らしやすさのタネ(住みやすい米原)
総合的空家対策
市では、平成27年に空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例を制定し、空家にしない、させない、ほっとかないを基本理念とする空家等の発生予防と地域ぐるみでの空家活用を推進してきました。しかしながら、条例制定から10年が経過する中、空家バンク事業の持続可能な体制の構築が課題となっています。
このため、地域おこし協力隊制度を活用して隊員2人を募集し、空家バンク事業の人材育成と実施体制の強化を図ります。さらに、空家にならないようにするための啓発や指導、危険空家の抑制など、空家の適正管理にもしっかりと取り組んでまいります。
移住定住の促進
東京への一極集中、特に女性や若者の流出が止まらない中で、地方の魅力や暮らしやすさを効果的に発信するとともに、移住に関心がある人や検討している人たちに米原市を深く知ってもらい、この地での暮らしを具体的にイメージできるアプローチが必要です。
移住についての相談対応やサポートを行う移住コーディネーターを設置するとともに、本市への移住を後押しする移住支援金、新幹線通勤補助金を拡充し、米原暮らしに踏み出す人たちを増やしていきます。
地域農業の担い手確保
地域農業を取り巻く環境は、農家数の減少や農業従事者の高齢化等による担い手不足、耕作放棄地の増加などの大きな課題があり、特に中山間地域では深刻な状況です。担い手確保、農地を守るということは、食料自給率の向上や環境保全、地域の農業文化や伝統が継承され、地域の活力にもつながります。こうした課題の解決に向けて、中山間地域である東草野地域における地域農業の担い手として地域おこし協力隊2人を募集します。
市民農園開設補助、まいばら農業塾園芸発展支援、スマート農業技術導入支援
小さく、無理なく始める新しい農業への入り口として始まった「まいばら農業塾」。塾生や修了生が農業を継続できる環境づくりや、新たに農業へ挑戦しようとする人の関心、理解を深めるため、市民農園の開設を支援するほか、販売に特化した野菜等の6次産業化や商品化、ブランディング等を学ぶ機会を提供します。
また、引き続き、先端技術を活用したスマート農業技術の導入を支援し、農業の効率化、省力化による生産性の向上を推進します。
(仮称)磯公園整備、大型遊具等がある公園
市民の皆さんから「公園や施設といった遊び場の充実」が子育てしやすいまちにとって重要であるとの御意見を多くいただいています。
現在、取組を進めています(仮称)磯公園の整備工事については、土地造成や雨水排水施設などの基盤整備工事に着手します。
また、私が公約に掲げております「大型遊具、水遊びのできる公園と雨天や冬季も遊べる施設の設置」については、身近に子どもとのふれあいや子育てを楽しめる場所として、市民の皆さんと一緒に検討してまいります。
重点4.元気のタネ(活気あふれる米原)
国スポ・障スポ大会
44年ぶりに滋賀県で開催される国スポ・障スポ大会。ホッケー競技の開催地として、あの時の感動を再び!を目指し、これまでリハーサル大会の運営や、おもてなしセミナーなどを開催し、市を挙げて大会に向けた機運醸成を図ってきました。
10月の本大会に向けて、市民の皆さんと一緒に盛り上げ、感動をわかちあい、記憶に残る大会に、そして、誰もが輝ける大会となるよう、更なる機運醸成と未来へレガシーを引き継げる大会運営を行ってまいります。
創業支援事業補助、にぎわい創出商業店舗開設補助、民間開発の促進
昨年、米原駅東口に地元企業を中心に進出いただくことが決定しました。今後は、この進出を契機として、駅周辺だけではなく、市内全域に人を呼び込み、まち全体が活気づくようなまちづくりを進める必要があります。
駅前などの中心市街地で飲食店や小売店の新たな開設を支援する制度の創設や、地域資源を生かしたり、地域課題の解決につながる創業を支援します。
また、良好な住環境を備えた魅力的な市街地の形成に向けて、民間開発を促進させる施策の具体的な検討を進めるほか、企業が求める新たな産業用地の確保および企業誘致に向け、引き続き、滋賀県の支援をいただきながら、長浜市と共同で取り組んでまいります。
重点5.飛躍のタネ(市民とともにつくる米原)
市制20周年記念事業、つながる米原
令和7年は市制20周年を迎えます。市政の進展に功績のあった方などの表彰や記念動画の上映、講演会の開催のほか、記念ロゴマークの作成、子どもたちや市民が苗を育て、伊吹山に移植する事業など、まちへの愛着や誇りを育む取組を進めます。
さらに、この節目を契機として、ふるさと納税や企業版ふるさと納税など将来的な財政支援や人材還元へとつなげるため、本市にゆかりや縁のある人たちが市の応援団になっていただけるような関係性を構築するためのPR活動など、まちの未来を育てる事業を通じて、ふるさとへの愛着、米原市の飛躍へとつながる一歩としてまいります。
行政経営改革の推進
人口減少と高齢化が進む中、市政運営においても限られた経営資源を最大限に活用し、職員一人一人が活躍できる環境を構築し、財政の健全化と質の高い行政サービスによる、持続可能な行政経営を進めなければなりません。
令和6年度に策定した米原市行政経営改革プランに基づき、人財育成、健全財政を進めることはもちろんですが、将来を見据えた未来への投資や中長期的な視点で、人口減少に対応できるまちづくりを進めるため、本市に適した規模となるよう公共施設の最適化も視野に入れた公共施設の在り方について検討を始めてまいります。
第3次総合計画
次の50年、100年後を見据え、人口減少社会においても、戦略的に立ち向かい、持続可能な地域社会の構築、地域と市のつながりを強固なものとしていくため、まちの羅針盤となる第3次総合計画では、市民や地域との対話を重視した計画づくりに取り組んでまいります。
総合計画の6つの基本目標に沿った主要事業
続きまして、第2次米原市総合計画に掲げる6つの基本目標に沿って、令和7年度の主な事業について説明します。
1.健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり(福祉)
まず、1点目「健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり」についてです。
子どもから高齢者まで、すべての人が地域で安心して暮らしていける地域共生社会の実現に向けた地域づくりを進めます。
地域のつながりが希薄化し、生活課題を抱えながらも身近な相談者がいないため、生きづらさを感じている人が増えています。複雑化・複合化した課題を抱えた家庭や個人などを総合的に支援する相談体制づくり、居場所づくりや就労支援などの社会参加への支援、地域の社会資源の発掘や人材育成を行う地域づくり支援の3つの取組を一体的に行う重層的支援体制整備事業を進めます。
高齢による認知機能の低下など権利擁護の必要な人の早期発見、早期段階からの相談支援、意思決定支援等、包括的な支援を行う権利擁護センターについて、令和7年度は専門家が参画する受任調整の仕組みを整備するなど、中核機関としての機能を強化いたします。
共働き世帯の増加や核家族化などによって、子どもを取り巻く環境は大きく変わっています。国において、子どもを社会の中心に据え、子どもの視点や権利を最優先に考える子ども・子育てにやさしい社会づくりが進められている中、本市では、家庭の養育環境等に課題を抱え、学校や家庭に居場所のない子どもへの居場所づくりを進めていくため、個々の課題に応じた支援を包括的に提供する児童育成支援拠点を、市内1か所で開設いたします。
本市では、むし歯がある子どもが県内でも多い現状です。むし歯予防は、従来の良好な食習慣の形成、歯磨きや歯科医による定期的な健診に加え、集団の場で取り組むフッ化物洗口を組み合わせることが効果的であり、推奨されています。そこで、永久歯が生え始める年長児の希望する子どもを対象にフッ化物洗口を行い、ブラッシング指導も合わせて実施することで子どもたちの歯の健康づくりを進めます。
2.ともに学び輝き合う人と文化を育むまちづくり(教育・人権)
2点目「ともに学び輝き合う人と文化を育むまちづくり」についてです。
学校、家庭、地域が連携しながら子どもを育み、互いに学び合い、人権を大切にし、多様な主体が共生できるまちづくりを進めます。
不登校児童生徒やいじめの認知件数が増加している状況の中、本市では、不登校児童生徒やその保護者に対して、居場所の提供やいじめ等対応支援員の配置などを行っています。しかしながら、児童生徒の特性、学校への行渋り、いじめに遭ったなどで困っている児童生徒、保護者、学校がどこに相談してよいか分からず、支援につながっていない状況もあります。こうした状況を受け、特別支援サポートセンター、みのりおよびステップ・フォワード・プログラム(SFP)を束ねる組織として、新たに教育支援センターを設置し、各機関の連携強化を図るとともに、保護者等からの相談窓口を一本化することで、利便性の向上に努めてまいります。
また、いまだに固定的な役割分担意識、職場環境、賃金格差などが男女共同参画の進展を阻んでいます。性別による差別や固定的な性別役割分担をなくし、多様な働き方や生き方を尊重する社会の構築を目指し、第5次となる男女共同参画推進計画を策定します。
3.水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり(環境・防災)
3点目の「水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり」についてです。
豊かな自然を守り、次世代に引き継ぐことを目指し、人と自然が調和した生活の実現と、暮らしの安全、安心なまちづくりを進めます。
米原市環境基本計画に基づき、2030年度までに市内の二酸化炭素排出量53パーセント削減を目指し、引き続き、営農型太陽光発電事業の着実な推進とスマートエコハウスの普及や次世代自動車導入促進を支援します。
また、新たなエネルギー資源として期待される水素などの多様な次世代エネルギーが活用される社会の実現も注視し、市民の暮らしや産業の脱炭素化を更に促進してまいります。
人口減少社会に対応した持続可能な消防団とするため、組織を再編した新体制による消防団活動への支援や待遇改善などを進め、市民の生命と財産を守る消防団が安心して活動できる環境づくりを進めます。
また、市内の小学校4年生を対象に、伊吹山の土砂災害を教訓とした防災教育「まいばら防災の子」に取り組み、子どもたちの防災意識の向上とシビックプライドの醸成へとつなげます。
4.地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり(産業経済)
4点目の「地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり」についてです。
産業を振興し、多様な働き方や働く機会を創出し、活気と活力に満ちたまちづくりを進めます。
今年開催される大阪・関西万博や国スポ・障スポ大会を契機として、大阪、京都、名古屋など大都市からのアクセスの良さを生かした交流人口の増加を目指し、観光地域づくり団体である一般社団法人びわ湖の素DMOや観光事業者と連携した市内の周遊観光キャンペーンや米原駅を核とした広域観光の取組を促進します。
5.心地よく暮らせるにぎわいと交流を支えるまちづくり(都市基盤)
5点目の「心地よく暮らせるにぎわいと交流を支えるまちづくり」についてです。
道路の強靭化を進め、地域の発展につながる道づくり、快適な住環境や公共交通ネットワークの整備を図り、住みやすさと利便性を高めます。
公共交通の充実は、市民意識調査の結果からも市民の満足度が低く、利便性の高い持続可能な公共交通の確保が求められています。地域公共交通の活性化、利便性向上のため、利用者の声を踏まえ、乗合タクシーまいちゃん号の予約締切時間を1時間前から30分前に短縮し、公共交通の充実を図ります。
市が管理する公営住宅は、最も古いもので建築から52年が経過し、老朽化による修繕等が頻発し、維持管理が難しくなっています。公営住宅の適正な維持管理を行い、居住性、安全性等の維持および向上を図るため、老朽化している公営住宅の予防保全的な修繕計画である長寿命化計画を策定します。
激甚化・頻発化する災害、老朽化する道路や水道・下水道など、市民の命を守り、安心を与える公共インフラの確保は重要です。安全安心な道づくりを進めるため、米原市道路網整備計画2024に基づき、設計や用地購入、工事に着手している道路整備を着実に進めるとともに、都市計画道路に認定されている市道碇高溝顔戸線(いかりたかみぞごうどせん)の交通量調査を行います。
また、全国で水道や下水道施設の老朽化による事故が発生し、社会生活に大きな影響を与え、市民の行政に対する信頼が低下する事態となっています。重要なライフラインである上下水道機能を確保するため、耐震化も含めた計画的な布設替え工事の実施や保守点検を行います。
6.まちづくりを進めるための基盤(都市経営)
最後に、6点目の「まちづくりを進めるための基盤」についてです。
人口減少社会において、持続可能なまちとして行政経営を進めるためには、市民、企業、地域団体といった多様な主体との連携を強化し、社会情勢の変化、市民ニーズに迅速に対応できる行政経営を進めていくことが必要です。
行政サービスの電子申請手続きの拡大、これまで書面や対面を前提としたものからオンラインへの転換が大きく進んでいます。行政サービスや暮らしのデジタル化を推進するため、自宅等のパソコンやスマートフォンからオンラインで手続が完了する電子申請システムを導入します。また、二次元コードを使った広聴システムを本格的に導入し、市民の皆さんの声を集め、それを分析して可視化することで、データに基づく政策形成に生かしてまいります。
全国の自治体では、職員の働き方改革の取組が進んでいます。本市においても市役所の開庁時間の短縮、時間外延長窓口の縮小を順次実施させていただきます。これは、職員の働き方を見直すことで、職員のやりがいやウェルビーイング、いわゆる心身の健康や幸福度を最大化し、より良い行政サービスの提供へとつなげることが目的です。市民の皆さまには何卒、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
結び
「蒔かぬ種は 生えぬ」という言葉があるように、成果を得るには 準備と努力が欠かせません。米原の大地となる、ひと、まち、暮らしを深く理解し、そこに可能性のタネを蒔き、生命を育むように、丁寧に愛情を注ぎ、必要な資源を注ぎ込むことで、初めて、まちの未来を 切り拓くことができるのです。私が市長となって本格的な政策を進める令和7年度は、米原市のシンボルである伊吹山の再生を目指すとともに、20周年を迎え、人口減少に対応できる、新たな未来への歩みのタネとなる施策を推し進め、しなやかな枝葉が茂り、立派な花や実となるように、市民の皆さんと一緒に育みながら、人口減少社会においても市民が幸せで心豊かに安心して暮らせるまち、『住み続けたくなる米原』の実現に向けて市政運営に邁進してまいります。
市議会議員の皆さまをはじめ、市民の皆さまに格段の御理解、御協力をお願い申し上げ、令和7年度の施政方針とさせていただきます。
- この記事に関するお問合せ先