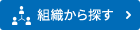令和6年 仕事納め市長訓示
更新日:2025年01月09日
今年も残すところ、あと数日となりました。
職員の皆さん、1年間大変お疲れ様でございました。お世話になりました。
今年を振り返りますと、1月1日に震度7を観測する能登半島地震が発生し、被災地を支援するために職員の皆さんに現地に行っていただくなど、大変な年明けとなりました。
そして、本市においては、7月に伊吹山で三度に渡り、土砂災害が発生しました。これまでに経験のない、長期間に及ぶ災害対応、避難所運営に昼夜を問わず、懸命に取り組んでいただきました。
被災された市民に寄り添った支援、関係機関と連携した災害復旧、迅速な県・国への緊急要望対応などにより、着実に伊吹山の再生に向けて、前へ進めていただくことができました。職員の皆さんに改めて敬意を表し、感謝申し上げます。
発災直後から、道路や砂防堰堤の土砂撤去、大型土のうの設置、雨が降る度にパトロールも実施していただきました。また、被災家屋を1軒1軒回り、被災された方の声を直接聞きながら、家屋調査を行い、円滑な対応をしていただきました。市民に寄り添って取り組んでいただいたことは、単なる災害対応だけに留まらず、その後の業務に活きていると聞き及んでおります。
さらに、植生回復のためのプロジェクトも着実に進めていただき、今年度シカの捕獲数300頭を目標とし、効果的な方法による捕獲強化で12月26日現在290頭の捕獲していただきました。
引き続き、災害復旧、伊吹山の再生を目指し、また、市民の安全・安心を守るために御尽力いただきますようお願いいたします。
災害が多い一年であり、重い話題からとなりましたが、今年は、米原市が未来に向けて大きく変化するタイミングの年でもありました。
まず、長年の懸案であった、米原駅東口周辺まちづくり事業で進出事業者が決定し、6月に基本協定が締結され、新しいまちづくりがスタートしました。このまちづくり事業を契機に米原市の賑わいづくりを加速させていただきたいと思います。
同じく6月には、平和希求の拠点となる「平和の礎」が完成しました。今月、小学6年生と中学生3年生を対象に平和学習が実施され、私も参加させていただきました。
戦後79年、戦争の記憶がない世代が多くなり、後世に受け継ぐことが難しくなりましたが、戦争の悲惨さ、命の尊さを学ぶこのような機会があることを誇りに思います。
子ども達にはこの体験を通して学び、感じた思いを忘れず、未来に伝えていただきたいと思います。
そして、9月には、国スポ・障スポ大会ホッケー競技のリハーサル大会が開催されました。開催に当たり、準備に御尽力いただき、多くの職員の皆さんに御協力いただきました。
来年は、本番を迎え、全国から多くの方が米原駅を利用されることになります。選手、関係者を安全かつ確実に競技会場に輸送するための円滑な運営はもちろん、競技の観覧や観光にお見えになる方々が米原市で足を止めていただける観光、経済活動などへの発展につながる機会となるよう、皆さんで盛り上げていただきたいと思います。
経済に目を向けますと、名目賃金は引き上げられてはいますが、実質賃金は依然として、物価高騰に追い付かず、市民生活への負担は大きなものとなっています。市民の安全・安心な暮らしを守ることは、我々、地方自治体の責務です。誰一人取り残されない社会の実現ために、市民に向き合い、市民に寄り添った施策を展開していかなければなりません。
私自身も市民や事業者の方々の声を聞かせていただく機会を積極的につくり、市民の皆さんの願いを実現する施策を展開したいと考えています。伊吹地域での災害支援で行っていただいたように、職員の皆さんも市民に丁寧に寄り添い、「希望と勇気が与えられる市役所」を目指して、来年も職務に励んでいただきたいと思います。
市長に就任して、約1か月半、多くの職員の皆さんからレクを受け、それぞれが抱えておられる課題や御苦労と合わせて、聞かせていただきました。
その中で、改めて感じたことは、仕事は点ではなく線として考え、さらには面で対応できることが必要だということです。担当課だけでは進められない課題も、横の連携を密にしてコミュニケーションを深めていただき、解決に向け、進めていただきたいと思います。
私も、教育長、新しく就任いただいく副市長、そして、すべての職員の皆さんに支えていただきながら、新しい市政運営を進めてまいりたいと思います。
結びに、今年の年末年始は9連休となります。
会食などが増えることと思いますが、事故・不祥事等を起こさぬよう、コンプライアンスを徹底いただくとともに、インフルエンザも流行しておりますので、健康には十分ご留意いただきたいと思います。
皆さんお揃いで、輝かしい新年を迎えられますことを、心から祈念し、仕事納めの挨拶といたします。
ありがとうございました。
- この記事に関するお問合せ先