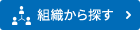米原市子ども条例
更新日:2025年04月16日
米原市では、子どもが心身ともに健やかに育つことができ、全ての人が安心して子どもを産み育てられる社会を実現することを目的として、平成26年4月に「米原市子ども条例」(平成26年条例第9号。以下「子ども条例」といいます。)を制定しました。
子ども条例では、子どもに対する基本的な考え方として、子どもは一人の人間として人格と権利を有していることを定め、また、児童の権利に関する条約で提唱されている4つの権利「生きる、育つ、守られる、参加する」を守り、保証することを大人から子どもへの約束として定めています。さらに、子どもにとっての最善の利益を「子どもの幸せ」と表現し、子どもの幸せを最優先に考えながら、子ども一人一人の成長を守り育てていくこととしています。
米原市子ども条例 子ども版 (PDFファイル: 725.4KB)
前文
子どもは社会の宝であり、未来をつくる力と希望です。
すべての子どもは、かけがえのない存在として、家庭や地域の人々に大切にされ、人との関わりの中で、愛情を実感しながら、それぞれの個性や能力に応じた成長をしていきます。
大人は、子どもの人権を守り、子どもの年齢や発達に応じた支援と見守りを行うとともに、誰もが家庭や地域の絆を大切にして、人と人とのつながりの中で幸せを感じられる子どもにやさしい社会を築いていかなければなりません。そして、子どもが生きる力を育みながら将来に夢と希望を持ち、協働の大切さを知り、郷土に愛着と誇りを持って、いつまでも住み続けたいと思えるまちにしなければなりません。
伊吹山や琵琶湖、ホタルなど美しい自然に恵まれたふるさと米原
地域の伝統行事や文化遺産に恵まれたふるさと米原
人と人の絆が息吹くふるさと米原
これらを後世に継承するとともに、次代を担う子どもの大切さを市民が共有し、子どもの育ちと子育てを社会全体で支え合う、元気と笑顔があふれるまち米原の実現を目指し、この条例を制定します。
目的
第1条 この条例は、子どもが心身ともに健やかに育つことができ、すべての人が安心して子どもを産み育てることができるよう、家庭、育ち学ぶ施設、地域、事業者および市(以下「各主体」といいます。)の役割を明らかにし、施策の基本となる事項を定めることにより、子どもの育ちと子育てを社会全体で支え合うまちを実現することを目的とします。
基本理念
第2条 子どもが心身ともに健やかに育つことができるまちづくりは、子どもの人格と権利を尊重することを基本として取り組みます。
2 子どもの育ちと子育ての喜びが実感できるまちづくりは、子どもの幸せを最優先に取り組みます。
3 子どもの育ちと子育てを社会全体で支えるまちづくりは、各主体の役割に応じて相互に連携し、協働して取り組みます。
(解説)
子どもに対する基本的な考え方として、子どもは一人の人間として人格と権利を有していることを市民全体で共有すべき事項として定めています。
さらに、まちづくりを進める上において、子どもにとって何が一番大切なことなのかを考え、また、その取り組み方は、子どもに関わる全ての人が、それぞれの立場から取組を進めていくことを定めています。
子どもにとっての最善の利益を、「子どもの幸せ」と表現し、子ども条例を運用する上で最も重要な基本原則となります。
定義
第3条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の者をいいます。
2 この条例において「育ち学ぶ施設」とは、学校教育施設、社会教育施設や児童福祉施設など、子どもが育ち、学ぶために利用する施設をいいます。
人権の尊重
第4条 大人と子どもは、基本的人権を尊重し、命を尊ぶとともに、人を思いやる心を持つことに努めなければなりません。
子どもへの約束
第5条 大人は、子どもが社会の一員であり、未来を担うかけがえのない宝であることを認識し、次の子どもの権利を守り、子どもの育ちを支援します。
(1) 命を大切にし、自分を愛し、自分らしく生きること。
(2) 夢と希望に向かって、健やかに育つこと。
(3) 守られ、安心して暮らすこと。
(4) 自分の意見を表明したり、主体的に活動できること。
(解説)
大人は、子どもが未来を担う存在であるとの認識のもと、その人材を育てるという観点から、子どもの幸せを最優先に考えながら、子ども一人一人の成長を守り育て支援していくことを示しています。
また、児童の権利に関する条約で提唱されている4つの権利「生きる、育つ、守られる、参加する」を守り保障することを、大人から子どもへの約束として分かりやすく定めています。
家庭の役割
第6条 家庭は、子どもにとって最も身近な社会で、成長の原点であることを理解し、次の役割を果たすよう努めます。
(1) 愛情とふれあいを大切にしながら、お互いの絆を深め、子どもの心身のよりどころとなる環境をつくること。
(2) 子どもとともに育ち合いながら、基本的な生活習慣や社会の決まりなどを身に付け、心身ともに健康な生活を送ること。
育ち学ぶ施設の役割
第7条 育ち学ぶ施設は、子どもの育成における社会的な使命を担うことを理解し、次の役割を果たすよう努めます。
(1) 子どもが集団の中で自ら学び、考える力などを身に付け、知識の習得や心身の発達を助ける教育を推進すること。
(2) 子どもの年齢や発達に応じた、学び遊ぶ場としての環境をつくること。
(3) 子どもや保護者が相談しやすい環境を整えるとともに、人権教育やいじめの防止に関する教育を推進すること。
(4) 家庭、地域および事業者と連携し、地域に開かれた環境をつくること。
地域の役割
第8条 地域は、日常のふれあいを通じて、子どもの社会性や豊かな人間性を育む場であることを理解し、次の役割を果たすよう努めます。
(1) 地域の絆を大切にしながら、子どもを見守り、子どもが安心して過ごせる環境をつくること。
(2) 地域の伝統や文化を伝承しながら、子どもが地域の一員として自主的かつ主体的に社会参加できるために必要な支援をすること。
事業者の役割
第9条 事業者は、その事業活動を通じて子どもの育成を支援することを理解し、次の役割を果たすよう努めます。
(1) 子どもとの関わりを深めることができるための職場環境をつくること。
(2) 家庭、育ち学ぶ施設、地域および市と連携し、子どもの育成に関する活動に協力すること。
市の役割
第10条 市は、子どもの育成について、次に掲げる役割を果たします。
(1) 子どもの育成に関する施策を総合的かつ計画的に実施すること。
(2) 家庭、育ち学ぶ施設、地域および事業者の相互の連携や協力による活動が促進するよう調整と支援を行うこと。
子育ての支援
第11条 市は、子どもを育てる力を向上させるための総合的な子育て支援を推進します。
2 市は、子育てと仕事の両立を支援する環境づくりを推進します。
3 市は、子どもの養育に関し、必要な支援に努めます。
安全で安心な生活の確保
第12条 市は、子どもの安全な生活を確保するための環境の整備を推進します。
2 市は、関係機関と連携し、子どもに対する犯罪の防止や子どもが安全かつ安心して育つ環境の確保に努めます。
3 市や地域は、子どもが安心して過ごすことができる居場所づくりに努めます。
(解説)
悪影響を及ぼす有害な社会環境の排除や犯罪の防止、子どもたちが事件や事故に巻き込まれないよう子どもを守るための取組、さらには子どもが成長していく上で必要な場所として「遊び、学び、集う」場とともに「心の居場所」の確保を進めます。
居場所とは、公園、公民館、公共施設などの施設や放課後児童クラブなど身を置く場所、さまざまな社会環境や自然環境の中で体験活動のできる場所を指します。さらに、人や地域とのふれあいの時間など自分の存在価値が実感できる「心の居場所」も意味します。
居場所は、大人たちが押しつけて与えるものではなく、あくまで子ども自身が居場所を見つけることができるよう、大人や地域などが支援していくことが大切です。
子どもの育ちの支援
第13条 市は、子どもが心身ともに健康的な生活を送るための支援を推進します。
2 市は、子どもに対する虐待、いじめ等の予防や早期発見に努め、関係機関と連携して、子どもの人権を守り、救済するために必要な措置をとります。
3 市は、子どもからの相談や子どもについての相談に対し、関係機関と連携して速やかに対応します。
(解説)
安心して子どもを産み、育てることができるよう、子どもの医療や保健対策の充実、子どもや保護者の心身の健康づくりへの支援を進めます。また、子ども自身からの相談や子どもの成長や子育てに係る不安や悩みを解消するための相談などの取組を進めます。
さらに、子どもに対する虐待やいじめなど子どもの人権や生命を守るとともに、救済するための取組や連携体制の強化を図ります。
「関係機関」とは、こども家庭センターや警察署などをいい、市と連携し、協力しながら速やかな対応をしていきます。
保育と教育の充実
第14条 市は、安全で安心な保育と教育の環境整備を推進します。
2 市は、子どもが年齢や発達に応じて健やかに成長できる保育と教育を推進します。
3 市は、子どもが豊かな心と感性を育み、生きる力を身に付けるための教育を推進します。
子どもの社会参加の支援
第15条 市は、子どもが意見を表明したり、社会に参加する機会を確保するとともに、子どもの意見がまちづくりに反映できるよう努めます。
2 市は、子どもが自然や地域社会とのふれあいの中で、郷土に愛着を持って心豊かに育つことができるための環境づくりを推進します。
(解説)
子どもは一人の市民として、まちづくりに参加する機会の確保や、自分自身の考えを表明できるようにする取組について定めています。
まちづくりを進めるためには、幅広い世代からの意見を聴き取ることが大切であり、次世代を担う子どもたちの意見を反映させることが多面的でよりよいまちづくりにつながるものと考えています。
家庭と地域の教育力
第16条 市は、家庭や地域において子どもを育成するために必要な教育力を高める取組を推進します。
施策推進の措置
第17条 市は、子どもの育成に関する施策を実施するため、財政上の措置などの必要な措置をとります。
基本計画
第18条 市は、子どもの育成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画(以下「基本計画」といいます。)を策定します。
2 市は、基本計画を策定するときは、市民の意見を反映することができるよう努めます。
3 市は、基本計画を策定したときは、分かりやすく公表します。
評価
第19条 市は、子どもの育成に関する施策を効果的に推進するため、基本計画に基づいて行った施策について評価します。
2 市は、基本計画に基づく施策を評価したときは、分かりやすく公表します。
推進体制
第20条 市は、子どもの育成に関する施策を推進するために必要な体制を整備します。
委任
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他の執行機関が別に定めます。
- この記事に関するお問合せ先