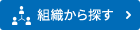「人間力」を育む教育の充実
更新日:2024年09月12日
教育実践の重点
「子どもたちが自分でつかむ自分の未来」の実現
1.各校の基本ビジョンをもとに「自己肯定感」と「自己有用感」の高揚を図る
- 日々の教育実践や学校行事の中で、子どもたちが自分の良さ、成長、可能性を実感できる場面を意図的に設定し、活動を積み重ねることで、一人一人が「自己肯定感」を高め、将来の夢をもつことができるようにする。
- 学校が今まで以上に地域や社会を意識し、発達段階に応じた社会貢献活動や地域人材の活用等を通じて、社会に開かれた教育課程を展開していくことで、一人一人が「自己有用感」を高め、自己の将来を見据えた志を抱くことができるようにする。
- 一人一人が、自己の夢や志を実現するために、「今、何をどのように学び、何ができるようになることが大切なのか」を考えさせていくことができるようにする。
命・人権を大切にする心の育成を図る
1.心に響く道徳教育の充実
- 考え議論する道徳科の推進を図るとともに、学校の教育活動全体を通じた道徳教育を推進し、一人一人の内面に根ざした道徳性と望ましい人間関係を育てる。また日常生活における挨拶の実践など、道徳的実践力の育成に努める。
- 人間は一人一人がかけがえのない存在であることを自覚させ、「自尊感情」、「自他の命を大切にする心」、「思いやりの心」、「望ましい人間関係を築く力」の育成や、生きることの素晴らしさを実感させるなど、全教育活動を通して「命を大切にする教育」の推進に努める。
- 家庭・地域と連携して、基本的な生活習慣の形成を促し、相手を尊重して行動できるようにする。また、自然や動植物に親しむことなどを通して豊かな心情の育成に努める。
2.人権感覚を高め、差別を許さない人権尊重の実践的態度の育成
- 根強く存在するさまざまな差別の現実に学び、人権問題についての正しい理解と認識を培うとともに、人権について幅広い学習を進め、人権尊重の実践的態度を育てる。
3.互いに支え合い、高め合い、いじめのない、いじめを許さない集団づくりの推進
-
学校教育活動全体を通じ、互いの人格や個性を尊重し合い、相互の深い理解と信頼の下に、一人一人が個性や能力を発揮し、支え合い、高め合える集団づくり、いじめのない、いじめを許さない学級・学校づくりに努める。
-
児童会や生徒会の自治的集団活動を充実させ、児童生徒による主体的ないじめ未然防止の取組を推進し、明るく楽しく全ての子どもにとって居心地のよい学校づくりを推進するとともに、いじめを許さない学校風土を醸成する。
-
いじめの問題に対しては、児童生徒に関わる全ての者が自らの問題として切実に受け止め、徹底して防止対策や早期発見・早期対応に取り組む。
-
いじめの問題に対する組織対応を推進し、スクールカウンセラー等との連携を図りながら、いじめの問題が解消するまで被害児童生徒及び保護者に寄り添った組織対応に取り組む。
4.健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくりに向けて、福祉教育の充実に努める
- 手話言語条例を尊重し、手話への理解を促進し、手話を学ぶ機会および手話に触れる機会の確保に努める。
自己指導能力の育成を目指す
1.豊かな人間性や社会性・規範意識を育む生徒指導の推進
- 一人一人の心に響く生徒指導を充実する中で、社会生活上のルールや基本的なモラルなどの規範意識を身に付けさせるとともに、自己存在感や自己有用感の育成に努める。
- 生徒指導の実践上の視点(自己存在感の感受、共感的な人間関係の育成、自己決定の場の提供、安全・安心な風土の醸成)に留意して、児童生徒が互いの立場や考えを尊重し、違いを認めて協力し合える学習集団づくりと授業づくりを推進する。これにより自主的・自律的に判断し、行動できる子どもの育成を目指す。
2.変化の著しい社会での自立を目指す教育の推進
- 将来にわたって夢をもち、自ら学び考え、目標に向かってたくましく生きていけることができるよう、変化の激しい社会に対応できる、しなやかに生きる力を育成する教育を推進する。
- 地域の教育力を生かした職場見学や職場体験等を通して、子どもが社会や地域の一員であることの自覚、一人一人に望ましい勤労観や職業観を育てる体系的・系統的なキャリア教育を推進し、子どもが主権者として積極的に社会参画する力の素地を養う。
- 学校教育全体を通じた、計画的、組織的な進路指導により、主体的に自己の生き方を考え進路を選択決定し、生涯にわたって自己実現を図れる子どもを育成する。
- 特別な支援が必要な子どもや、虐待、ヤングケアラーやLGBTQ等に起因する子どもの困り感や悩みの早期発見に努め、学校連携マネージャーや関係機関等との連携により、子どもに寄り添ったきめ細かな指導・支援に努める。
(注)ヤングケアラー…一般に、本来本人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども
(注)LGBTQ…性的マイノリティ(性的少数者)を表す総称のひとつ
体力の向上と健康の保持増進を図る
1.運動に親しみ体力の向上と心身の健康の保持増進を目指す教育の充実と食育の推進
- 体育科や学校行事、部活動等、教育活動全体を通して運動に親しませ、運動習慣の確立と体力の向上を図るとともに、健康・安全についての自己管理能力を高め、生涯を通じて心身ともに健康で活力のある生活を営むことができる健康や体力を養う。
- 「みんなで伊吹山に登ろう」をテーマに、ふるさとの山に登ることで、体力の向上と感動体験の共有を図るとともに、環境保全について考えるきっかけとする。
- 家庭や地域社会、保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校の連携を深めるとともに教育相談活動の充実を図り、心身ともに健康で安全な生活を送るための基本的な生活習慣・態度の育成に努める。
- 健康な心身を育むとともに、望ましい食習慣の習得を目指して、学校の教育活動全体で食育の推進に努める。
- 防災教育や交通安全教育を通じて、自分の命はもちろん友達を含めた自分の周りにいる人々の安全も大切にすること、災害発生時には自分たちに何ができるのか主体的に考えることなど、「防災リテラシー」の育成に努める。
具体的取組
- 発達支持的生徒指導として、日々の教職員の児童生徒への挨拶、声かけ、励まし、賞賛、対話及び授業や行事等を通した個と集団への働きかけに努める。
- スクールカウンセラーによる心理授業などSOSの出し方に関する教育を実践する。
-
「学校いじめ防止基本方針」の定期的な見直しを行い、全職員で共通理解を図るとともに、いじめ問題が発生した場合は、「学校いじめ防止基本方針」を基に、教職員が一丸となって組織的に対応する。
-
教育相談やいじめに関するアンケート等を計画的に実施し、いじめの早期発見・早期対応に努める。
-
生徒会の役員として、各校の取組を交流し、自校の取組に活かす生徒会フォーラムを開催する。また、共通実践として「つながろう米原!LOVE&PEACEプロジェクト」を推進する。
-
地域の協力を得て、中学校2年生の職場体験学習を実施する。
- この記事に関するお問合せ先